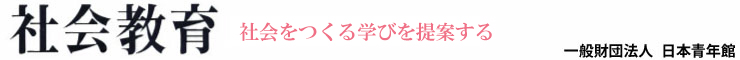
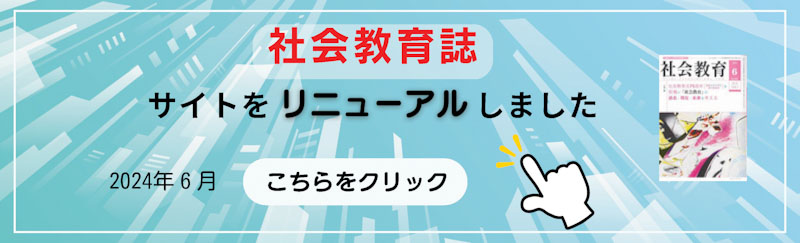 ~ 社会をつくる学びを提案する 生涯学習社会の学術総合情報誌 ~ 当ウェブサイトは移転しました 現在バックナンバーはこちらからご参照いただけます。 なお、バックナンバー以降のページは情報が古いままですので、 何卒ご了承のほどお願い申し上げます。 |
|
■ HOME |
|
|
財団法人全日本社会教育連合会は財団法人日本青年館と2012年10月18日に合併し、
2012年11月号より月刊誌「社会教育」は、財団法人日本青年館が発行することになりました。 また、財団法人日本青年館は、2014年4月1日より一般財団法人日本青年館となりました。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
|
日本青年館 公益事業部 「社会教育」編集部 〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4-1 日本青年館5階 TEL 03-6452-9021 FAX 03-6452-9026 (C) 2012~2024 Nippon-Seinenkan. All rights Reserved. |